| 長距離走行において、ハンドルポジションの多いドロップハンドルはフラットハンドルよりも楽です(一般論)。 MTBにドロップハンドルを取り付けることについては賛否両論のようですが、上手くできればかなり良いツーリング車になります。 ロードレーサーやシクロクロスというよりも、ランドナー(特に26HEランドナー)に近い自転車だと私は考えています。 「なら最初からランドナーにすれば?」と言う人がいますが…手持ちの愛車を自分オリジナルの未知の自転車にカスタム してしていくという面白さがあるんですよねぇ(^-^)。ここでは私が実際にやっている方法、確認済みの方法を紹介します。 パーツの組み合わせ方等はシクロクロスと同じなのでそちらも参考にしてみてください。 |
 ハンドル |
 ステム |
 シートポスト |
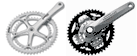 クランクセット |
 STI |
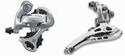 ディレイラー |
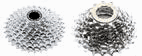 スプロケット |
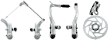 ブレーキ |
 ブレーキレバー |
 シフトレバー |
|
フラットハンドルを前提に設計されたMTBフレームのトップチューブは、ロードフレームのトップチューブよりも長くできています。
なので、ドロップハンドルをMTBに取り付ける場合はリーチ(ハンドルの突き出しの長さ)の短いタイプをお勧めします。
例を挙げると日東 B105RD-浅曲がり・チネリ
ダイエットエビオス・TNI ビクトリーバーなど色々あります。
下の写真は(左)普通のドロップハンドル(日東ニートMod114-STI)、(右)ショートリーチタイプ(TNI ヴィクトリーバー)の比較です。 左はリーチ92mm、右は65mmです。違いが分かりますか?  
左はSTIが前に突き出ていますが、右の方はかなり手前にSTIがにあります。 目安としては、リーチ100mm以上は長すぎだと思います。今MTBについているステムはだいたい100mm前後のはずです。 ドロップハンドルにして+100mmとなると…かなりSTIが遠くなります。その分ステムで調整すると、かなりステムは短く… ハンドリングもクイックに。ということで、リーチ80mm以下(もしくは前後)が目安になると思います。上に挙げた例意外 にも、リッチーのドロップハンドルもリーチ80mm前後と小ぶりです。 ただ、リーチが短い分当然見た目も変わってくるので、「短ければ良い」というものでもないかも知れません。 ある程度はステムでカバーできるので、バランスを考えて色々と試してみるのも面白いです。 あと、日東の中にはB105RDのように、MTBと同じクランプ径(25.4mm)のハンドルがあるので、この場合は、MTBのステムが そのまま使えます。 |
|
まず、ドロップハンドルとステムのメーカーは同一にするのが基本です(メーカーによってハンドルのクランプ径がばらばらな為)。
ドロップハンドルにはリーチ(突き出し)があるのでそれを踏まえて、ステムの長さはフラットハンドルの時に使用していたステム よりも短いものを選んだほうが良いでしょう。ステムに関しては、ハンドルとの兼ね合いが在るので試行錯誤が必要かもしれません。 参考までに私は身長175cmでハンドルのリーチ65mm(TNIビクトリーバー)、ステムの長さが85mm(TNI)。 ただし、極端に短いものは、 ハンドルがクイックになりすぎるので注意。 因みに、「オーバーサイズ(OS)のMTBのフォークコラムにロードのステムは取り付けできるの??」と思う人もいるかも知れませんが、 心配は要りません。最近のロードのステムはノーマルサイズ(1インチ)だけでなく、オーバーサイズ(OS)に対応しているので、MTBに も取り付け可能です。ただし、前述のようにハンドルを固定する部分の径はメーカーによってバラバラなので注意してください。 |
ハンドルのリーチも短く、ステムもそれなりに短くしても、なんとなくハンドルが遠い…という場合は、シートピラー
を変えてみましょう。シートピラーには「オフセット」があります。これだけで、結構変わります。
|
| ドロップハンドル仕様のMTBで一番難しいのがクランクセットとFディレイラーの選択です。 因みに、一番無難なのは、MTB用クランクセット&MTB用Fディレイラーをそのまま使用する 事です。 |
| ★ MTBのクランクセット |
 ほとんどの方はMTBのクランクセットを使っているようです。私も無難なMTB用クランクセットを使用しています。
因みに、MTBのクランク+MTBのFディレイラー+デュアルコントロールレバー(シマノSTI)での組み合わせでは、
変速できるのはギア板2枚分です。「インナー×ミドル」か「ミドル×アウター」のみです。
ほとんどの方はMTBのクランクセットを使っているようです。私も無難なMTB用クランクセットを使用しています。
因みに、MTBのクランク+MTBのFディレイラー+デュアルコントロールレバー(シマノSTI)での組み合わせでは、
変速できるのはギア板2枚分です。「インナー×ミドル」か「ミドル×アウター」のみです。
私は、インナーを取り外して「ミドル×アウター」で使用しています。なかなかすっきりとしていて良いです。 |
| ★ ROADのクランクセット |
 MTBフレームのチェーンステイは、泥はけを良くするために大きく横に膨らんでいるので、ロード用のクランクセットを
取り付けるとチェーンステイと干渉してしまう恐れがあります。下の写真はブリヂストンアンカーのMTBフレーム
にTIAGRAのトリプルクランクセットを取り付けた様子です(左クリックで拡大)。
MTBフレームのチェーンステイは、泥はけを良くするために大きく横に膨らんでいるので、ロード用のクランクセットを
取り付けるとチェーンステイと干渉してしまう恐れがあります。下の写真はブリヂストンアンカーのMTBフレーム
にTIAGRAのトリプルクランクセットを取り付けた様子です(左クリックで拡大)。
シートステイとインナーチェーンリングの間隔が1~2mmほどしかあいていません。勿論、 フレームによっては完全に干渉して回らないことも…。でも結局インナーチェーンリングにはまともに変速できないので、 干渉するようなら取っ払ってダブルにするのもありです。 ダブルのクランクセットを取り付ける場合は、BBを軸長の長いトリプル用にして、チェーンステイとチェーンリ ングの間隔を空ける必要があります。以下は全く未確認ですが、BB一体型のクランクセット(ダブル)の場合、ステーと干 渉する恐れがかなりあるので、トリプル用のBB一体型クランクセットを選択して、インナーを取り払う方が無難かも知れ ません。一体型の場合はBBの軸長で誤魔化せないので…。 変速に関しては、ロードクランクセットTIAGRA(FC-4403 トリプル)・MTB用FディレイラーをDEORE(FD-M511)・ロードSTIを 105(ST-5501)の組み合わせで変速の確認をしたところ、ワイヤーを取り付けていない状態でもインナーには変速しませんでした。 (たまたま変速することもありますが…稀です。ギアを使い切った場合は手でインナーに…。)原因はおそらくインナーのチェ ーンリングが内側に入りすぎているため。BBの軸長を更に長いタイプにすると変速可能かもしれませんが…チェーンラインの 関係でリアの変速が上手くいかなくなるかもしれません。因みにこの組み合わせで、ディレイラーをロード用にするとどうな るかは未確認です。  手でインナーにチェーンを掛けた様子。ディレイラーはこれ以上内側には行かない。
走行は可能なので緊急用としては十分使える。(左クリックで拡大)
手でインナーにチェーンを掛けた様子。ディレイラーはこれ以上内側には行かない。
走行は可能なので緊急用としては十分使える。(左クリックで拡大)結論 クランクセットはまだまだ研究が必要ですね。。今の時点で言える事は、STIとの組み合わせでは、 クランクセットはMTBでもROADでも確実に変速できるのはギア板2枚分のみです。 まずは、フレームに合うのか(チェーンステイと干渉しないか)。そして、オフロードを走るのか、オンロードのみを走るのか、 見た目はどうしたいか…など目的別に使い分けると良いと思います。 |
(※シマノ製デュアルコントロールレバー使用の場合) |
| ★ Rディレイラー |
|
ロード用Rディレイラーはもちろん、MTB用Rディレイラーでも正常に作動させる事が出来ます。 |
| ★ Fディレイラー |
|
・MTBのクランクセット+MTBのFディレイラーで使用する場合 ギア板2枚分しか変速できません。つまり、「トップ×ミドル」か「ミドル×ロー」のどちらかになります。 殆どの人はインナーを取り外して使っています。 ・ROADのクランクセット+MTBのFディレイラーで使用する場合 トリプルの場合は「ミドル×アウター」が可能。「インナー」は△。手で入れれば緊急用ギアとして使えますが。 (上のクランクセットの項目参照) ダブルの場合、チェーンリングがフレームに干渉する事を防ぐために、BBはダブル用 ではなく軸長の長いトリプル用にした方が良いです。 |
| |||||||||||||
| ★ MTB用スプロケの場合 | |||||||||||||
|
RディレイラーはMTB用を使用します。シマノはギアの歯数が最小11~最大34Tまであります。歯数がワイドなので峠越えや路面の
変化が大きいオフロードにお勧めです。 | |||||||||||||
| ★ ロード用スプロケの場合 | |||||||||||||
|
Rディレイラーはロード用・MTB用どちらでも構いません。シマノはギアの歯数が最小11~最大27Tまであります。
11 12 13 14 15 16 17 19 21tのようにロードのスプロケットは歯と歯の差が少ない(クロスレシオ)です。ということは、
最後まで1~2tずつしか変化しないので、変速したときに「重すぎ、軽すぎで丁度いいギアが無い!」ということがなく
なり路面やその他状況にあわせた適度なギアで安定した走行ができます。要するに、ある程度安定した道なら適度なギア
で楽に速く走れるということです。ただし、最大の歯数はMTB用の最大歯数よりも少ないので当然一番軽いギアにしてもMTB用のとき
のように軽くはなりません。上り坂でギアが無くなれば・・・。そのため荷物を積んだ長距離のツーリング等には厳しいかもしれません。
と言っても、クランクセットがMTB用のままならまず大丈夫ですが。
目的に応じて選んでください。ちなみに私はキャンプツーリング以外はだいたいロード用を使用。 といっても、最近はどんな条件でもロード用ですが…使い分けとしては、普段は11~23t。 大きな峠越えや坂が多いコースの時は12~25tのスプロケを使用。それよりもきつい条件が予想される場合は11~32tのMTB用を使用。 |
| ★ カンチブレーキ | ||||||||
普通はカンチブレーキを使用します。レバータッチが一番自然です。カンチ・Vブレーキ台座があれば取り付け可能です。
最近はVブレーキのシューを使うカンチブレーキが増え、シューの調整が簡単です。例として
Avid ショーティ6やTESTACH、シマノBR-R550など色々とあります。あと、カンチブレーキにはアウター受けという小さな部品が必要です。フロントはフォークコラムに取り付けるタイプ(写真:左)と
フォークにあけられた穴に取り付けるタイプ(写真:真中)があります。サスフォークの場合は、フォークコラムに通すタイプを選択します。
リアのアウター(写真:右)はシートピンのところに取り付けます。



「カンチブレーキはきかない」という事をたまに聞きます。確かに今のVブレーキやディスクブレーキと比べると制動力は弱いです。 (逆に言えばVブレやディスクが強力なんですがね…。) ただし、一言にカンチブレーキと言っても、価格も性能もピンキリで色々 と違いがあります。長らくAVIDのショーティ6を愛用していますが、余程の劇坂の下り以外は、特に不満を感じた事はありません。 さすがにシマノALTUSクラスのカンチだと不満爆発だと思いますが…。因みに、千鳥ワイヤーの角度が不 適切な場合などでも、制動力が落ちるので注意が必要です。 | ||||||||
| ★ ミニVブレーキ(ショートアームカンチブレーキ) | ||||||||
ミニVブレーキという方法も一応あります。しかし、少々調整がシビアです。
リムとシューの間隔は1~2㎜ほどしかなく、リムが振れるとすぐにシューが擦っ
てしまいます。ここまで間隔を狭めてもブレーキレバーを強く握るとハンドル
につきそうになります。ただし、Vブレーキは制動力があるので、十分効くといえ
ば効きますが…。
 また、ギリギリまでワイヤーを引っ張って固定するので、タイヤを外す際にブレーキ を解除出来ない事があります。その場合、上の写真(一番右)のようにリードパイプの 端をカットすると解除しやすくなります。ただし、何らかの原因 で不意に外れる事を防ぐ為に、切り過ぎには注意してください。この加工は自己責任 でお願いします。安全のため蛇腹のVブレーキブーツは付けておきましょう。 不意の外れ防止に役立ちます。 正直なところ色々な理由から、素直にカンチブレーキにしたほうが楽です。ブレーキ タッチもカンチブレーキの方がかなり自然な感じです。 | ||||||||
| ★ Vブレーキ & メカニカルディスクブレーキ(MTB) | ||||||||
| Vブレーキと機械式ディスクブレーキは、カンチブレーキやロードのキャリパーブレーキとはレバー比が異なる為、 ロード用のレバーでは上手く機能しません(自己責任でそのまま使用している人もいますが)。Vブレーキで試したところ、 レバーをハンドルに付くほどいっぱい握っても、シューはほんの僅かしか動きません。「なにこれ??」って感じです。。 ただし、下記の小物を使うことで正常に作動させる事が可能です。 | ||||||||
| ||||||||
| ★ メカニカルディスクブレーキ2(ロード用) | ||||||||
|
|
① どうやってもフロントギア3枚変速したい! ② STIやエルゴ等のデュアルコントロールレバーは意外と高価…。もっと安上がりにドロップハンドル化! ③ スプロケットが6S・7S・8Sでデュアルコントロールレバーが手に入らない場合。 ④ もしくは7S用・8S用の古いレバー、中古のレバー、グレードの低いレバーが気に入らない場合。 ⑤ 軽量化? | ||||
| ★ バーエンドコントローラー(通称:バーコン) | ||||
| ||||
| ★ その他シフター | ||||
ブレーキレバーはカンチブレ-キであれば普通のロード用・ランドナー用ブレーキレバーで問題ありません。Vブレーキ・普通の機械式 DISKの場合はVブレーキ対応のダイアコンペ 287Vを使用すると良いでしょう。287Vが気に入ら ない場合は、ロード用のブレーキレバー+トラベルエージェントなどの小物の組み合わせでOKです。詳しくはブレーキの項目を参照。 |
Topへ










